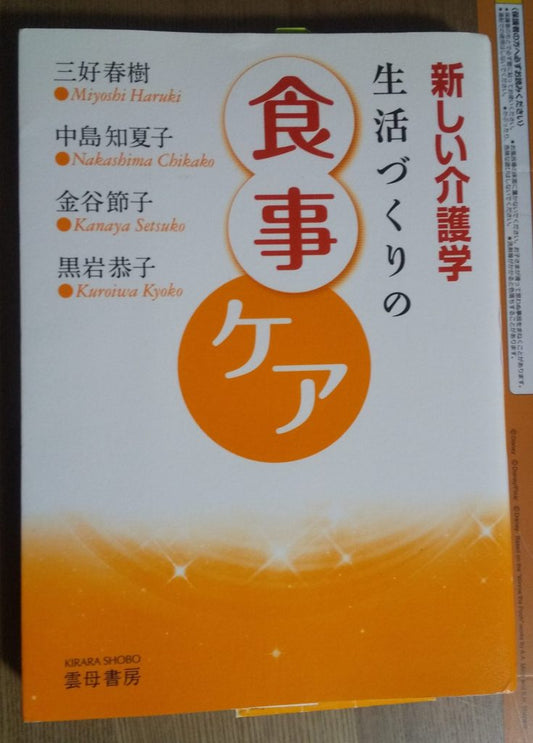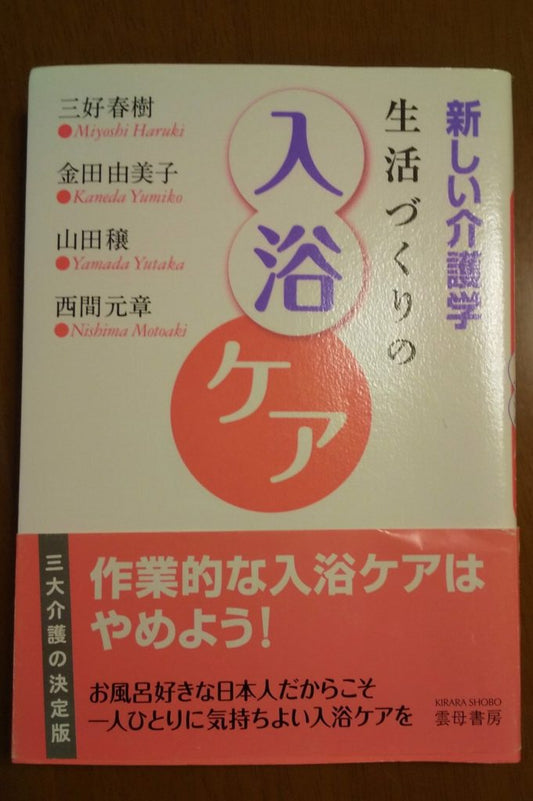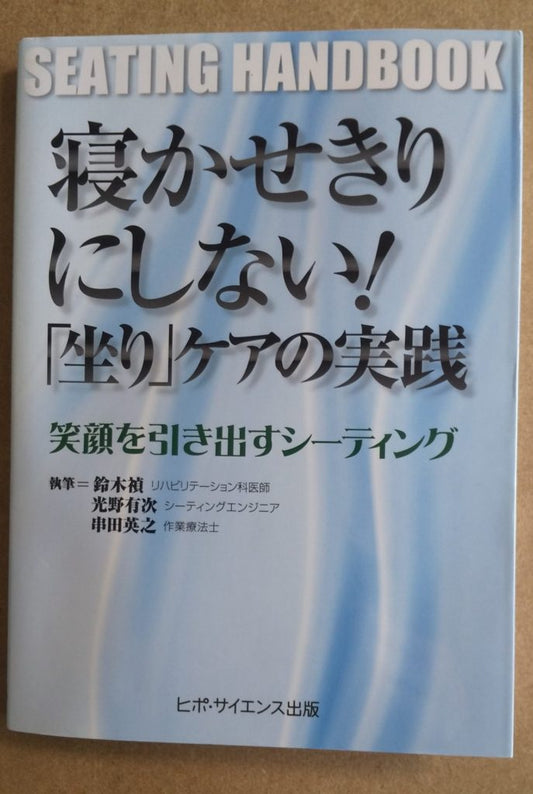リハビリ

旅行に行くとき、いつも気になること
どこに行くにも快適に安全に過ごすことができればいいのですが、歴史ある場所では必ずしもバリアフリー化が進んでいるわけではありません。 職業病かもしれませんが、仕事の視点も少し織り交ぜながら、趣味の旅行に時々出かけています。 楽しみを皆で共有できる街づくりが大事だなと思う今日この頃です。
旅行に行くとき、いつも気になること
どこに行くにも快適に安全に過ごすことができればいいのですが、歴史ある場所では必ずしもバリアフリー化が進んでいるわけではありません。 職業病かもしれませんが、仕事の視点も少し織り交ぜながら、趣味の旅行に時々出かけています。 楽しみを皆で共有できる街づくりが大事だなと思う今日この頃です。

訓練量の目安
訓練強度や量を増やすことで、神経・筋の機能レベルからADLレベル、自宅退院率やうつ病予防など社会的側面にも効果は増大すると報告されています。 また、脳卒中治療ガイドライン2021では、「脳卒中後の運動障害に対して、課題に特化した訓練の量もしくは頻度を増やすことが勧められる」と記されています。
訓練量の目安
訓練強度や量を増やすことで、神経・筋の機能レベルからADLレベル、自宅退院率やうつ病予防など社会的側面にも効果は増大すると報告されています。 また、脳卒中治療ガイドライン2021では、「脳卒中後の運動障害に対して、課題に特化した訓練の量もしくは頻度を増やすことが勧められる」と記されています。

動くためには感覚が大切
リハビリスタッフとさまざまな内容のリハビリをする中で、「動かしている感じがわかりますか?」や「握っている感じがわかりますか?」など感覚に関する質問を受けて、「麻痺しているのにどうして感覚について質問されるのかな?」と疑問を持ったか方もいらっしゃるでしょう。
動くためには感覚が大切
リハビリスタッフとさまざまな内容のリハビリをする中で、「動かしている感じがわかりますか?」や「握っている感じがわかりますか?」など感覚に関する質問を受けて、「麻痺しているのにどうして感覚について質問されるのかな?」と疑問を持ったか方もいらっしゃるでしょう。

脳卒中後、なぜリハビリ実施のために評価を行うのか
手足が思うように動かない状態のときに、「手を挙げてください」と体の動きを確認するような検査も行われたと思います。 脳卒中後、自分自身の体の状況を理解することが難しいときに、さまざまな評価を実施されること自体が苦痛に感じてしまうことがあったかもしれません。
脳卒中後、なぜリハビリ実施のために評価を行うのか
手足が思うように動かない状態のときに、「手を挙げてください」と体の動きを確認するような検査も行われたと思います。 脳卒中後、自分自身の体の状況を理解することが難しいときに、さまざまな評価を実施されること自体が苦痛に感じてしまうことがあったかもしれません。

歩行のパフォーマンスと歩行パターン
歩行の実用性を高める要素として、「安全性・安定性・耐久性・速度姓・社会性」の5つであると言われています。 この実用性の5つの要素をみてみると、「歩行のパフォーマンス」の要素が多いことがわかります。 歩行のパターンは歩行のパターンとの関連性がありますので、歩行について考えるとき、しっかりパフォーマンスとパターンについて把握していきたいと思っています。
歩行のパフォーマンスと歩行パターン
歩行の実用性を高める要素として、「安全性・安定性・耐久性・速度姓・社会性」の5つであると言われています。 この実用性の5つの要素をみてみると、「歩行のパフォーマンス」の要素が多いことがわかります。 歩行のパターンは歩行のパターンとの関連性がありますので、歩行について考えるとき、しっかりパフォーマンスとパターンについて把握していきたいと思っています。

脳卒中後の麻痺手のリハビリにおける目標設定
麻痺手のリハビリにおいて、目標を設定することで、モチベーションが高まり麻痺手の使用頻度が多くなることがわかっています。 麻痺手の使用頻度が高まると、日常生活での成功体験が増え、さらにモチベーションが高まり麻痺手の使用頻度が増え、麻痺手の使用頻度依存の脳のネットワークの再構築が促進されます。
脳卒中後の麻痺手のリハビリにおける目標設定
麻痺手のリハビリにおいて、目標を設定することで、モチベーションが高まり麻痺手の使用頻度が多くなることがわかっています。 麻痺手の使用頻度が高まると、日常生活での成功体験が増え、さらにモチベーションが高まり麻痺手の使用頻度が増え、麻痺手の使用頻度依存の脳のネットワークの再構築が促進されます。